2017/06/26(月)メインPCのRAID0化
デスクトップに組み込んで、もともと使ってた2TBと合わせて、Windowsのストライプボリュームにしてみた。
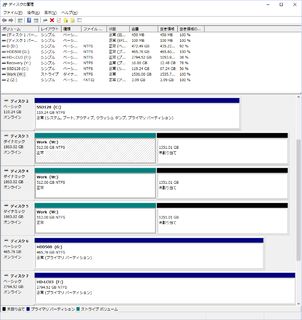
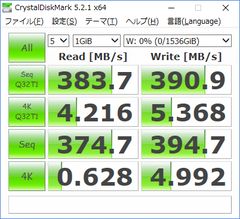
当初Readが微妙に遅かったのだけど、BIOSでSATAコントローラのモードをAHCIからRAIDにしてみる*1となんかRead速くなった。
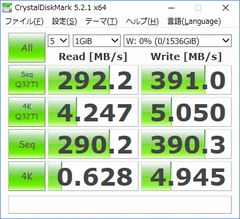
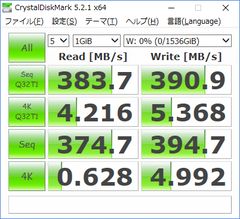
コントローラの設定をRAIDに変えたので、Intel RSTで、RAID0にしてみた(128Kストライブ)もためしてみる。
4Kが微妙に速い。
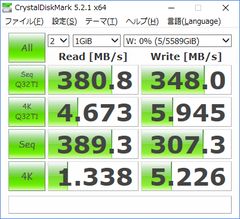
大きめのファイルをコピーしてみたりの使用感はあんまり変わらない感じ。
600MBのファイルは、コピーダイアログなしでコピーできる。
3GBくらいのファイルは、どっちでやっても10秒くらい。
序盤2GB/sとかでて、1GBくらいのところからスローダウンするようなグラフになる。
IntelRST使ってもWindowsのダイナミックディスクでも、この感じもあまり変わらない。
キャッシュの使い方が似てるんだろう。
Intel RSTを使う利点は、容量が可変なこと(と、Windowsから1つのディスクとして見えるのでタスクマネージャがうるさくならないこと)。
WindowsのDynamicDiskを使う利点は、ディスクアレイの一部をRAID 0に、一部をRAID1に みたいな使い方ができることかなぁ。
一回使い始めちゃうと、データの逃げ先を用意しない限り変更できないから悩む。
目的は、でかいデータの作業用領域で、
ほとんどシーケンシャルアクセスだから4K速度はまぁどうでもいいし、
今回は、後者のメリットをとって、Windows標準のRAIDにしてみようかしら。
まぁ、SSDと比べては微妙か。
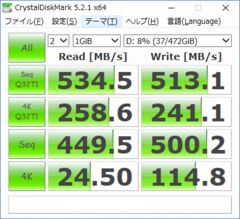
というよりも、SSDを作業領域に回して、HDDは普通に使った方がいい気がちょっとしてきた……。
